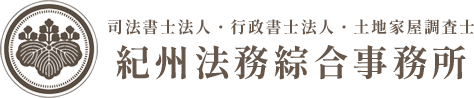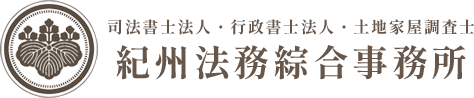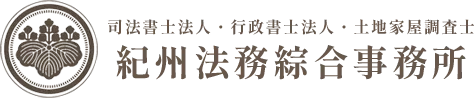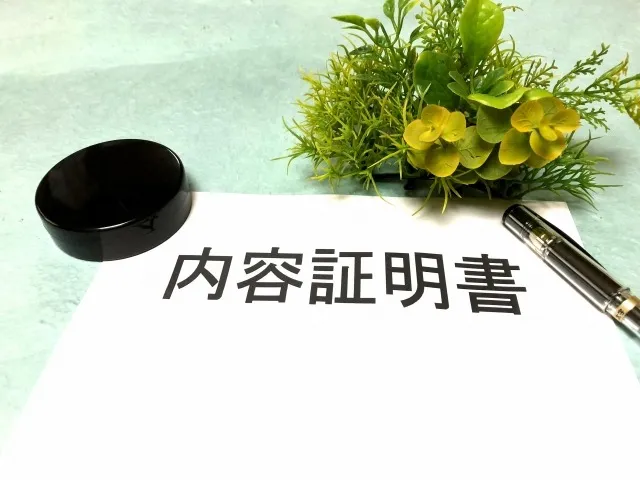相続登記の義務化とは?
2025/06/27
令和6年4月(2024年4月)に改正不動産登記法が施行され相続登記が義務化されることとなりました。この改正は、相続によって取得した不動産の名義変更を速やかに行うことにより、相続人が適切に権利を主張でき、またトラブルを未然に回避できるように手続きを義務化したものです。今回は、相続登記の義務化に関連する制度の詳細について解説します。
目次
そもそも相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を亡くなった所有者から相続人に変更する手続きのことです。不動産の所有者の管理はその不動産の所在地を管轄する法務局で行われており、相続登記は管轄の法務局に対して所有権移転の登記を申請する形で行われます。相続登記を怠ると、不動産の売却や担保設定が困難になる可能性があり、相続人にとって大きな不利益をもたらします。
相続登記の義務化が導入された背景とは?
相続登記の義務化は、近年深刻化している「所有者不明土地問題」への対策として導入されました。相続登記の義務化の改正が行われるまでは不動産の所有者が亡くなっても不動産の名義を変更する義務はなく、すでに所有者が亡くなっているにもかかわらず法務局の登記簿に古い所有者の名前が残り続けるといった状況が多く見られました。この状況では、災害復興や公共事業でその不動産を利用することが困難になるなどの問題が生じます。また、手続きを行わずに長年放置し続けると相続人の中からさらに亡くなる方が出てきてしまい、亡くなった所有者の相続人の相続人といったように関係者がねずみ算式に増えてしまいます。こうなってしまうと、いざ手続きを行おうとしても、膨大な労力と時間が必要になります。このような問題を解決するべく、令和6年4月(2024年4月)より相続登記が義務化されることとなりました。
相続登記の義務化の具体的な内容
「決められた期限内に名義を変更しないと最大10万円の過料に科しますよ!」というのが相続登記の義務化です。ちなみに「過料」とは行政罰の一種で、前科がつかない行政上のおとがめのことです。もちろん過料でも支払い義務はありますし、悪質な場合は過料でも財産を差し押さえられます。
決められた期限については、それぞれの状況により以下の3つのパターンに分かれます。
① 遺言や法定相続分で不動産を相続するパターン
→ 所有権取得を知った日から3年以内
亡くなった方の遺言により不動産を相続する場合又は民法が定める法定相続分に乗っ取って所有者の名義を変更する場合については、被相続人である不動産の所有者が亡くなったことを知ったこと及び自分が相続人であることを知ったときから3年以内に手続きを行わないと過料に科されます。
② 遺産分割により不動産を相続するパターン
→ 遺産分割が成立した日から3年以内
亡くなった方の相続人同士で話合いを行い遺産分割協議を経て不動産の名義を引き継ぐ者が決まった場合には、その遺産分割協議が成立した日から3年以内に手続きを行わないと過料に科されます。
一般的には、②の期限よりも①の期限が先に到来します。遺産分割協議の話し合いを行っている間に①の「所有権取得を知った日から3年以内」の期限が到来する場合は、一度法定相続分で相続登記を行い、改めて遺産分割協議後に遺産分割協議の結果と登記を一致させる必要があります。
③ 令和6年4月1日(2024年4月1日)より以前に相続が開始しているパターン
→ 不動産の相続を「知った日」から3年以内 または 施行日から3年以内のいずれか遅い方
令和6年4月1日(2024年4月1日)より以前に亡くなられた方の不動産の名義変更手続きについては、令和6年4月1日(2024年4月1日)より以前に被相続人である不動産の所有者が亡くなったことを知り、自分が相続人であることを知っていた場合は、相続登記義務化の施行日である令和6年4月1日(2024年4月1日)から3年以内に手続きを行わないと過料に科されます。つまり、令和9年3月31日(2027年3月31日)までに相続登記をする必要があります。
この改正の肝は、上記③で記載した通り、令和6年4月1日(2024年4月1日)の施行日以降に発生した相続だけではなく、過去に発生した相続に関しても義務化の対象になるという点です。また、相続登記の義務化と関連して不動産の所有者の氏名や住所が変更した場合の住所等変更登記の義務化の改正法の施行日も近づいております。令和8年4月1日(2026年4月1日)より住所等変更登記も義務化され、怠った場合には5万円の過料が科されます。相続登記の義務化と同じく施行日以前の変更も対象であり、こちらについては施行日から2年以内に申請が必要です。
相続登記の義務化の過料を回避する方法 相続人申告登記とは?
相続登記の義務化の過料を回避する方法として、相続登記を行うこと以外には相続人申告登記があげられます。相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴い新たに導入された制度です。相続人の間で遺産分割協議が難航している場合などに「私は、相続人です!」と法務局に届け出ることにより相続登記の義務を果たしたことになり過料が科されなくなる制度です。
相続人申告登記を使用する上での注意点は、相続人申告登記を行っても所有権は相続人に移らないという点です。相続人申告登記はあくまでも一時的な先延ばしであり、難航している遺産分割協議など相続登記ができない理由が解消されると相続登記を行う義務が生じます。
相続人申告登記は、相続登記に比べると簡単書類で手続きが可能であり、急いで相続登記の内容を決めなくて良い点でメリットがあります。また、個人単位で可能な手続きであるため他の相続人の同意が不要な点も大きなメリットです。
なお、相続人申告登記以外でも、相続人が多数で戸籍等の収集に時間がかかる場合や相続人自身が重病であり手続きが困難な場合などの正当な理由を法務局が認めた場合には過料は免除されます。
相続登記の重要性:権利を守るための第一歩
相続登記の義務化は、導入されて間もない制度であり、具体的な運用のされ方についてはまだまだ未知の部分が多いのが現実です。ただ、相続した不動産の登記手続きは必須となり、相続人はこの手続きを怠ることができなくなったことは事実です。司法書士は、この相続登記をスムーズに進めるための重要なパートナーで法律の専門知識を駆使して、相続人の確認や必要書類の準備、登記申請の代行を行います。 また、複雑な手続きを簡単にし、相続人が安心して手続きを進められるようにサポートすることができます。この機会に相続登記の重要性を理解し、何が適切な対応かご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。